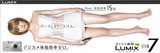「わが世界観」, 「運動会で1番になる方法」
「わが世界観」, 「運動会で1番になる方法」
「わが世界観」

以前保坂さんのエッセイを読んだ時に、彼がシュレーディンガーさんの本に言及していたのに興味を持って、今回読んでみました。実は保坂さんが引用してたのはこちらの本じゃなくて、「精神と物質―意識と科学的世界像をめぐる考察」の方だったよう。でもこの本も面白かった。
あとがきでも書かれていますが、シュレーディンガーさんは合理的神秘主義者と言われ、ウパニシャッド哲学の「梵我一如」こそこの世の真理だと書いています。近代の科学者は、外的世界の (意識・精神世界とは切り離された) 実在性や、意識の多元性などを前提として置いているが、そういった仮定こそが問題を複雑化させていると説いています。意識の基礎となる肉体は世界に属していて、全ての肉体は単一の世界に属しているとすれば、全ての意識は単一のものと言える、というその説明は、非常に明解なもので面白かった。
「意識」とは何か、という点についても、「まだ無意識化される前の生きるための方法論」のようなものではないか、ということを書いています。交感神経系のような現在の人類には意識できない神経の動きも、かつて意識的に体得した神経の動きが反復されるうちに無意識化されたものであって、意識的な動きをたくさん持つ人類という種はまさに、進化の途上にある、というのですね。特に社会性昆虫との対比において、ハチやアリが (たぶん) 無意識に社会のための利他的な行動を取り得るのに対して、人間はあくまでも意識的な倫理やモラルといったものに頼らなければいけないところを見ると、まだまだ社会性生物としてはハチやアリに及んでいない、進化途上の生き物なのではないか、と述べています。すごく面白い。
「運動会で1番になる方法」

僕自身は、運動会が非常に憂鬱な行事であるような子供 (すなわち運痴) だったんですが、子供達は今のところ案外運動好きのようなので (有葉はチョー運痴ですが…)、こういう本を読んで一緒に走り方を練習したら面白いかなぁ、と思ったんですよね。こないだの幼稚園の運動会で、柊次が2人ごぼう抜きしてリレーでトップになったのにびっくりした、というのも大きいです(笑。俺の子供とは思えん…。
本当に簡単なことしか書いてないのに、昔から言われているような「ひざを高く上げろ」とか「腕をしっかり振れ」というような、いわゆる速く走るためのセオリーが軒並み否定されてたりする。曰く、昔のセオリーは速く走れる人の動きを真似しているだけだったそうで、形だけ真似ても力を入れるべき筋肉の場所とかタイミングが身体でわかっていないとまったく意味がないとのこと。
さて、いつから始めよう…。