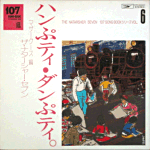Musical Baton
いつもバトンを渡し損ねる男、Digitune です…なんて言ってるそばから、またしても aeterna さんたらこりずにバトンを送ってきてくれました。今度は昔ナツカシ Musical Baton です。まだ続いてたんだぁ…。というわけで、がんばって答えてみます。途中、音楽とはぜんぜん関係のない話題に脱線することも多々あるかと思いますが、暖かく見守っていただきたく(笑。
Total volume of music files on my computer (今パソコンに入っている音楽ファイルの容量)
5.3Gbytes。曲数にして 1,140 曲くらいみたい。僕は一人のアーティストなりのアルバムを全部集める、といった CD の買い方をしないほうなので、つまみ食い的に雑多なものがちょろちょろ、という感じ。かなり昔に、手持ちの CD を全て ogg vorbis 160Kbps(VBR) 形式でリッピングしてしまって以来、実はそれほど増えていません。そのとき勢いで全部 vorbis でリッピングしてしまったのがその後ずっと尾を引いて、携帯プレーヤ選びのボトルネックになりつづけています(笑。ちょっと前までの vorbis デコーダは、フリーとはいえ浮動小数点演算が必須で、携帯プレーヤのような組み込み系には見向きもされていなかったんですよね。本家から整数演算のみのデコーダがリリースされた後、ようやっとあちこちのプレーヤでサポートされるようになりました。僕はご存知の方はご存知の通り(?)、Linux Zaurus に MediaPlayer 用の ogg プラグインを入れて、携帯プレーヤとして利用しています。
Song playing right now (今聞いている曲)

 …って言われても、今は何も聞いてないよっ!と言ってしまうとつまらないので、一番最後にちゃんと聴いた曲、ということにしましょう。とするとたぶん、遊佐未森さんのアルバム、「瞳水晶」より「瞳水晶」です。確かこないだお掃除してた時にでっかい音で鳴らしてたはず。
…って言われても、今は何も聞いてないよっ!と言ってしまうとつまらないので、一番最後にちゃんと聴いた曲、ということにしましょう。とするとたぶん、遊佐未森さんのアルバム、「瞳水晶」より「瞳水晶」です。確かこないだお掃除してた時にでっかい音で鳴らしてたはず。
遊佐さんのアルバムは「瞳水晶」と「空耳の丘」、それから「ハルモニオデオン」くらいしか聴いていないのですが (古っ!)、結構好き。前の前の会社に、寡黙で渋い、元銀行系のシステムベンダーに勤めていたとってもかっこいい先輩がいたんですが、彼が遊佐さんの大ファン、という話を偶然聞いてちょっと意外に思ったことを思い出しました。
The last CD I bought (最後に買ったCD)

 むむむ。最後に CD を買ったのももう何年も前だぁ…。はっきりいって覚えてないので、とりあえず谷本君のアルバムにしてみました。音楽 DVD も入れてよければ、多分間違いなく谷本君の「シャドウズ・アンド・ライツ」だろうし。
むむむ。最後に CD を買ったのももう何年も前だぁ…。はっきりいって覚えてないので、とりあえず谷本君のアルバムにしてみました。音楽 DVD も入れてよければ、多分間違いなく谷本君の「シャドウズ・アンド・ライツ」だろうし。
谷本君とは、偶然深夜の NHK に「耳汁」(とんでもない芸名だ・笑) という名前で出演しているところを見かけ、そのとき彼の弾いていた「渡り鳥」という曲がとても印象に残って、それからしばらくしてふと Google 先生に聞いてみたところ偶然彼のページを見つけ、それからメールをやり取りするようになって、東京に演奏に来てくれた時などに時々訪ねていくようになりました (彼は北海道の人なのです)。その後、いろいろなところで活動していたようなんですが、少し前からぱったり情報が途絶えてしまって、今はもう演奏活動はしていないのかな。ジャンルとしては「ニューエイジ・ギター」と呼ばれるものなのだそうで、基本的にはギター一本のインストなんですけれども、なんだかいろいろ面白い弾き方をして、多彩な音を聞かせてくれるのです (同ジャンルでは最近ですと押尾コータローさんなどが有名ですね)。アルバム、DVD に収められた曲は全て谷本君が書かれたものなのだそうで、それらの曲のフィーリングが個人的にとても合った、というのが僕が谷本君に惹かれた一番の理由かもしれません。彼の最後(?)の DVD、「シャドウズ・アンド・ライツ」には奏法解説なんかも入っていて、山のてっぺんでギターをかき鳴らしていたり、幅広い年齢層のお客さんが集まるコンサートの模様から彼の演奏や人となりが分かって、なかなかお薦め。
人からもらった CD まで含めると結構最近にもいろいろあって、この間の誕生日には弟にラフマニノフのピアノコンチェルト1番&2番とシンフォニー2番の CD をもらいましたし (なんでラフマニノフか、はこちらをご参照あれ)、元同じ職場の先輩である「お金持ちになりたい」さんにはSUPERCARのベストアルバムを2枚セットでもらっちゃいました。ありがたや。
Five songs (tunes) I listen to a lot, or that mean a lot to me (よく聞く、または特別な思い入れのある5曲)
なんだか僕の音楽人生総ざらい、という感じになっちゃいそうな予感がするけど(笑、頑張って行ってみましょー!あ、そうだ、単位は「曲」じゃなくて「アルバム」で行きたいと思います。
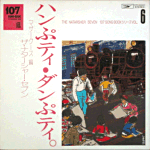
- ザ・ナターシャー・セブン「ハンぷティ・ダンぷティ。マザーグース編」
フォークシンガー高石ともやとナターシャセブンが歌うマザーグースの唄。上記リンク先は復刻された CD「マザーグースの唄」の買い方を説明してくださっているページで、今回調べてみて初めて知ったんですけどなんと今でも 2000 円でアルバムが買えるみたい。これは買うしかっ!
さて話を戻すと、僕がまだ小学生の頃、両親が買ってきたこのアルバムを僕ら兄弟はいたく気に入って、それこそすり切れるほどよく聞きました。子どもの頃にあんまりよく聞いたものだから、今でもアルバムの先頭から終わりまで通して歌えそうな勢いです。有名なマザーグースの曲、「猫とフィドル」「きらきら星」「黒ツグミ」「スカボロフェア」といった曲が全部で 42 曲も入っていて、一曲一曲の間にほとんど切れ間がなく、一つの物語のようにずっと続きます (ときどききちんと間が取られている箇所もある)。内容も基本的にはギター、マンドリンなどと男性ボーカルの構成ですが、アカペラがあったり、子どもの歌があったり、すごく個性的な女性ボーカルの曲があったり、曲によってはドラマ仕立ての音声の後ろを流れる BGM として流れていたりと、とても多彩です。
どの曲もかなり原曲のメロディに忠実に作られているようで、訳詞にしてもそうです。例えば、一般的には「きらきらひかる、おそらのほしよ」と歌われることの多い「きらきら星」も、このアルバムでは「きらり、きらりちいさなほしよ、あなたはとってもふしぎ」という歌詞になっています。谷川俊太郎さんや永六輔さんなんかも参加されていて、谷川さんの歌声が聞けたりします。
僕に、音楽の楽しさを教えてくれたのはこのアルバムかもしれません。僕にとってはそんなふうに特別に思い入れのあるアルバムだったので、先日の城田さんの事件を知った時は、さすがに少しショックでした。人間、長いこと生きていると、いろいろなことがあるのだな…と改めて思いました。


- ゲームサントラ「MOTHER」
さて気を取り直して2枚目。他の人の Musical Baton を読んでみると、この「思い入れのある5曲」にはほぼ必ずといっていいくらい「初めて買ったレコード (CD)」が入っていてちょっとおかしかったんですが、僕もその例に漏れず、これが初めて自分で買った CD でした (確か高校生の頃だから、「初めて CD を買う時期」としてはとっても遅いですね^^;)。「MOTHER」といえばご存知糸井重里さん製作のファミコン RPG。当時僕ら兄弟はこのゲームにすっかりハマってしまって、サントラから攻略本 (「MOTHER 百科 (Encyclopedia MOTHER)」というちょっと立派な本だった) まで買ったのでした。「MOTHER」の何がいいって、まず電車でしょ、スノーマンに最初にたどり着いた時の景色と音楽でしょ、マジカントの不思議さ、お城の音楽、そしてフライングマン、最後のイヴのメロディ。「歌」が重要なキーになっているせいか、全編を通して音楽は今でも素晴らしかったと思います。
「MOTHER」の音楽はムーンライダーズの鈴木慶一さんと任天堂の田中宏和さんの手によるものです。それまでも僕は結構ゲームミュージックを聞いていたので (ゲーム雑誌についていたソノシートをテープにダビングして一所懸命聴いてた・笑。ダライアスとか、バブルシステム起動音とか…。「アウトラン」の曲なんかは自分でピアノで弾いていたっけなぁ)、この「MOTHER」のサントラもこれまでのそれらと同じようなものだと思っていたんですよね。が、全く違った。何しろピコピココンピュータサウンドを期待していたところ、一曲目からいきなりの女性ボーカルにすっかり度肝を抜かれました。でも、最初の驚きが去ってからじっくり聴いてみると、ゲームの音源を単に収録したような「ゲームのサントラ」というレベルでは全くない、とても素晴らしいアルバムなのだと気がつき、すっかりお気に入りになったのでした。
このアルバムがとても気に入った僕は、これらの曲を作った「鈴木慶一」という人にも興味を持つようになりました。彼はムーンライダーズというバンドの人らしい。というわけで、とりあえず当時すでに発売されていたベスト盤をレンタルして聴いてみたところ、これがまたすごいカルチャーショック!「MOTHER」のサントラは一曲一曲非常に完成度が高くてある意味とても優等生的な音楽だったのに、ムーンライダーズの曲ときたら変な曲ばっかりで、歌もよく言えば荒削り、悪く言えば音を外しまくりだし、歌詞もエロくて変、最初は「なんなんだこれはっ?!」という印象でした。それでも、これも最初の驚きが去ってじっくり聴きなおしてみると、その非常にユニークで音楽性にあふれる曲にだんだん惹かれていきました。「青空のマリー」とか「僕は走って灰になる」とか超名曲だよね。最近のアルバムも実はイイ。最近あんまり CD 買ってないんだけど、彼らのアルバムならまた買ってみるか、という気にさせてくれます。単一のアーティストのアルバムとして、一番たくさん持っているのはたぶん彼らのアルバムだと思う。


- EBI「ミュゼ」
ユニコーンのベーシスト、EBI くんのファースト・ソロ・アルバム。ユニコーンもすごく好きで、当時世・妹の知り合いの人 (全くの見ず知らずの人・笑) にアルバムをテープにダビングしてもらって、擦り切れるほど聴いていました。このアルバムもそうやってダビングしてもらったものの中に含まれていたのですが、最初は「聴くと必ず寝てしまうアルバム」ということであまり聴いていませんでした(笑。ユニコーンって思いっきりアッパーな音楽じゃないですか。このアルバムはどちらかというとダウナーな感じで (中には「プログレな恋人たち」のようにはじけた曲もあるんですけど)、当時はあんまり好きじゃなかった。ちなみに僕自身は後で知ったんですが、このアルバムのプロデュースも実は高橋幸宏、鈴木慶一、岡田徹、かしぶち哲朗、白井良明というムーンライダーズの面々 (+幸宏さん) なんですよね。
そんな感じで最初の頃はあまり聴いていなかったこのアルバムですけれども、20歳の頃にあった大きな転機(笑)の後、夜あまり眠れなくなってしまって、このアルバムを睡眠薬代わりにしてずーっと聴いていました。それこそほんとに、1年くらいずーっと。そんなわけで、このアルバムは僕の身体の一部のようになってしまって、今でも時々聴くとなんだか妙な気分になります。そういう意味で、「特別な思い入れのあるアルバム」です。
そういえば、前の前の会社に入ったばかりのころ、とんでもなく大変な仕事のためにオフィスに一人で徹夜仕事をしているときに、たまたまかけていたラジオの深夜プログラムでリクエストを募集していて、疲れてちょっと気分が変になっていた僕は、会社の FAX からこのアルバムの中の曲、「八月の漂流者」を確か恥ずかしいメッセージ付きでリクエストしたんですよね。その後もずっと仕事を続け、残念ながら僕のリクエストはかからなかったんですけれども (こんなマイナーソングじゃ当たり前だ>俺)、翌朝、出社してきた女性の先輩社員の方にそのリクエスト FAX を発見されてしまって、ひどく恥ずかしい思いをしたことを思い出しました。うーん、恥ずかしい思い出の数なら誰にも負けない自信があるなぁ(笑。


- 新実徳英「日本合唱曲全集「幼年連祷」新実徳英作品集(1)」
上であげたレコードの影響なのか、僕は小さい頃から歌を歌うのが好きで、小学生時分にはよく授業中に歌を歌っては先生に怒られていました。歌好きな性分はその後もずっと変わらず、中学生の頃は合唱祭も大好きだったし、課内クラブでは男子生徒がほとんどいない「コーラスクラブ」を選んだりしていました。ちなみにこのコーラスクラブでは、男子は2人しかいなかったのに恐れ多くも「ハレルヤコーラス」なんぞに挑戦して、発声法などもろくに知らないくせにガーガー声を張り上げてました(笑。そんなこんなで高校生になって、それまでとはレベルの違う高校コーラス部の大人な魅力(笑)にすっかり当てられた僕は、半ば必然のようにコーラス部に入部し、以降3年間歌いつづける学園生活を送ることになるわけです。
作曲家、新実徳英との出会いは、高校に入ってからです。高校に入って最初の年、当時2年生でメイン・コンダクターだった H 先輩が、年間を通して練習して仕上げる曲として新実さんの「幼年連祷」を選び、1年間みっちり練習したことが始まりでした。それまで本格的な「合唱曲」のことを何も知らなかったので、最初は「変な曲」くらいにしか思いませんでしたが (特に「熱」とか)、その年はメイン曲が「幼年連祷」だったために、ある種“新実徳英イヤー”のような感じとなって、文化祭その他でも新実さんの他の曲をいろいろ歌うことになりました (「やさしい魚」など)。今思うと、そうやって本格的な合唱との出会いが新実さんの曲との出会いであったことが、僕が新実さんの曲を好きな理由の一つなのかもしれません。
「祈りの虹」は、その新実徳英作曲の原爆を扱った曲です。高校生の頃に先輩の作ってくれたテープで初めて聴いて強烈な印象を受け (男声合唱版でした)、以来、僕の中で「いつか歌いたい曲」No.1 の地位をずっと占めています。ただ、なにぶん難しい曲なのでなかなか歌える機会は訪れずに、楽譜とこの CD だけは入手したものの未だ時分では一度も歌ったことがありません。ただ、いざきちんと歌う機会が訪れたとしても、ちゃんと歌える自信はあんまりないかも…。「祈りの虹」や小林秀雄作曲「落葉松」は僕にとってあまりにも思い入れが強すぎるので、途中で声が出なくなってしまうような気がする。


- JUDY AND MARY「MIRACLE DIVING」
最後の一枚は何にしようか迷いましたが、ご存じ JUDY AND MARY 史上最強のアルバム、「MIRACLE DIVING」にしました。このアルバムに関しては、「思い入れがある」というよりも「好きな」アルバム、という感じかな。
JUDY AND MARY は、もともと僕というより弟が好きで、僕は彼の影響で聴き始めたようなところがあります。このアルバムが出た当時、僕はなぜかレコード店頭用マルチメディアキオスク向けコンテンツ作成の仕事をしていて、Sony Magazines の「WHAT’s IN?」編集部に月に一度入り浸って新譜の試聴盤をデジタルフォーマットにオーサリングする、という作業をしていました。ハードスケジュールの中で多数のコンテンツをオーサリングしてまとめなければいけないという仕事上、一つのタイトルにかけられる時間はせいぜい1コーラス聴いてサビを探す程度だったんですが、このアルバム発売後のツアーの様子を納めたライブビデオ (「MIRACLE NIGHT DIVING TOUR 1996」げげ、もう10年近く前だ…) には思いっきり引き込まれてしまって、最後まで通して見てしまった上、興奮して真夜中に弟に電話してがーがーしゃべりまくったりしました。今思うとさぞや迷惑だったに違いない(笑。
関係ないけど、ジュディマリの YUKI ちゃんとか TAKUYA って、ちょうど僕らと同年代なんですよね。彼らががんばっているのを見ると、僕らもがんばらにゃ、という気がしてきます。
ふぅ…。これでおしまい。長すぎですね。最後までめげずに読んでくれた方、ほんとにどうもありがとう。
さて、バトンを回す人5人ですが、ここは悩んでも仕方ないので、えいやっと書いちゃいます。自分の名前が書いてあってもあんまり気にせず、めんどくさければ華麗にスルーしていただけると助かります。
- お一方目は、すでに誰かから回ってきて一度答えられている可能性大、な気もしますが、元同僚で尊敬する先輩、KenG さん。音楽、と言えば KenG さんですよ。はい。
- お二人目はいつものかぴのすけ。なにかっちゅーと投げてスマン。
- 三人目は高校時代の素敵な先輩、単二さん。単二さんと僕は結構音楽の趣味が近いんじゃないかと思っているんですが、いかがでしょう…?
- 四人目は、やっぱり過去にとってもお世話になった、「φ’s」さん。ファイズさんは mixi 日記でよいですので…(弱気)。
- 最後は、素敵な好青年、明るい未来の担い手、「おっ」くん。おっくんと一緒に仕事してたときはあんまり音楽の話はしませんでしたよね。どんな音楽を聴いているのか、ちょっと興味があります。
11/8 から書き始めて、全部書くのになんと約 10 日もかかってしまった。いやはや…。
 最近の読書, 首都高チャレンジ
最近の読書, 首都高チャレンジ